「クックックック、ユリアよ、このくらいでまいってもらっては困るぞ。まだ一本しか入れておらぬしな…」
グローデのその言葉に応えるように、例の怪異な触手口から、もう一本の太い男根が鎌首をもたげて現れた。そして既に膣を犯している一本目のルートをなぞるように、ユリアの下半身にむけてするすると伸びていく。
「あ!はぁ、ああ、あああん!…きゃああああ!!」
官能の渦に翻弄されながらも、ユリアはその二本目の男根の存在に気づいた。しかし、ガッチリと身体を固定され、あまつさえ膣口に突き立てられた肉棒に蹂躙されている最中の少女に何ができようか。男根は何の妨害も受けぬまま、M字型に開かれたユリアの下半身へ悠々と向かう。そのターゲットとは…

ユリアはグローデの触手によって、下半身の穴という穴を陵辱されてしまった。太い肉棒は情け容赦なく子宮口を突き上げ、堪えきれずユリアは身もだえする。そのたびに、ヒクヒクとアヌスがすぼまり、そこを犯している肉棒に快感を伝えた。たまらずアヌスをグローデが突き上げると、今度は秘唇の肉壁が激しく収縮する。二本の肉棒は時には同時に、時には別々のタイミングでそれぞれのターゲットを突き上げ、ユリアを蹂躙する。細い触手のうち一本は包皮をムキ上げ、クリトリスに巻き付くと、そのムキ出しにされた神経の塊を念入りにしごきたてる。そして時には右に左に、優しく捻りながら振動を送り込むことも忘れない。あまりのことにユリアはただただ痙攣するばかりだ。
その一方で、もう一本の細い触手は、先ほどユリアが失禁したばかりの尿道口へと浅く先端を挿入すると、小刻みな震動を送り込んでいく。その異様な感覚の前には、もはや王女としての、いや、人間としてのユリアの尊厳など粉々にうち砕かれていくだけであった。
「はうううっく…はああ、あ、あああ、んああっ、いやあっ!だめえぇ…え…!しっ、死んじゃうぅ!」
そう言いながら、くねくねと身もだえするユリアの姿は、とても一国の王女には見えなかった。ラル王国の宝石と言われ、近隣の星系にまで評判の届いていたユリアであったが、グローデの責めの前になすすべもないその姿は、屈服した雌奴隷以外の何者でもなかった。

…限界であった。グローデのような男にリバースの秘密を話せば、生き残ったラルの民だけでなく、宇宙全体を危険にさらすことになる。王女として、民を売るようなことは最も許されぬことである…当然、ユリアもそのことは理性ではわかっていた。いや、むしろ全宇宙を見渡しても、ユリアほどに聡明で慈悲深く、国民を愛する王族はいないであろう。だが、そんなユリアでさえ、もはや自分のことしか考えられぬほどに精神が追いつめられていた。それほどにグローデの責めは常軌を逸していた。
度重なる羞恥と性感の嵐の前に、ユリアの意識は朦朧とし、思考が混濁していた。背中を弓なりにそらせ、ガクガクと身体を振るわせるユリア。そんな彼女に対し、なおもグローデは肉棒を叩きつけ続ける。
「お願い…秘密を話します!だから…たすけて…たすけて!あああ…死んじゃうぅ…もう…ゆるしてええええ!!」
しかし、そのユリアの哀願に対し、グローデが口にした言葉は予想外のものであった。
「秘密?…ふん、お前などに教えてもらわねばならぬ秘密などないわ」
そう言うと、グローデは触手の動きを一旦緩めた。そしてあざけりの笑いを漏らしながら、言葉を続けた。
「リバースの剣と呼ばれたものはただのナマクラ剣で、本当に魔力を秘めていたのは、伝説の剣士が持つ腕輪であった…そうだろう?」
「!?…なぜ…それを…」
「言ったであろう。我はずいぶん前からこの星に調査員を送り込んでいたと。その程度のことは全て調査済みだ。むろん、伝説の剣士とやらが、キャロンという小娘であることも知っておる」
「…キャロンさまのことも…!」
「…もっと言ってやろうか?そのキャロンという小娘こそが、実は本当の王女で、ユリア、お前は替え玉なのであろう?」
「…な!!!」
「…ふふ、リバースの腕輪のダミーとして役立たずのナマクラの剣があり、そして真の王女のダミーとしてお前がいる…なかなか面白いシナリオだ。一度くらいは知らずに騙されてみてもよかったかのう…ウワッハッハッハ!」
高笑いをするグローデの姿を、呆然とユリアは眺めていた。
(そんな…では…なぜグローデは私をさらってきたの…秘密を聞き出す目的もないのに…この辱めも秘密を聞き出すためものだと…)
「クククク、状況が理解できぬという様子だな。愚かな奴よ。いいか、よく聞け。我はな、いかにしてお前を辱めるか、ということだけを考えておったのよ。たかが人間の小娘の分際で、狂おしいまでの気品と優しさ、美しさを兼ね備えた存在である、お前をな。リバースの秘密を知らぬフリをしたのも、陵辱を彩るためにすぎぬ。民を思う心と、責めの辛さの板挟みになるお前の姿、美しくも滑稽であったわ!ウワッハッハッハ!」
「そ、そんな…そんな…」
「クククク…だが、そのお前も、結局屈服した…。フフフ、民を愛する優しい王女と言われたお前が、責めに堪えかね、とうとう民を裏切った…!しょせんお前も人間、自分の身の方が可愛いのだな。我は、高貴ぶった人間が堕ちていくのを見るのが大好きでのう。なかでもお前はとびきりであったわ…」
あまりの衝撃に、ユリアはもはや、何らの言葉も口に出来なかった。肉体のみならず、ユリアはその心までもドス黒い魔物に弄ばれてしまったのだ。
「だがな、我を怨むなよユリア。もとはといえば、お前がニセ王女になどならなければよかったのだ。お前は自分が偽物だと知りつつも、十数年間、民を騙し続けてきたのであろう。そう思うと、我はラルの民が哀れでならぬ。ニセの王女を敬愛しつづけ、しかもそのニセの王女はというと、敵の愛撫によがり狂い、国の興廃に関わる秘密をもあっさりとばらすような裏切り者であったわけだからな。いやはや、可哀想なラルの民よ。涙なしには語れぬのう」
およそ涙などとは縁のないような滑稽な調子でグローデはそう言うと、さらに言葉を続ける。
「…そこでな、ユリア。心優しい我は、ラルの民を慰めてやりたくなってのう。少し変わった嗜好をためさせてもらったぞ」
そう言うと、それまで暗闇に包まれていた部屋のうち、壁の一面が突然白く輝きだした。
「あれはな、スクリーンと言ってな。まぁ、映像を映す装置とでも思ってくれ。今、面白いものをみせてやる」
そのグローデの言葉にこたえるように、壁のスクリーンに映像が映し出された。星空に四つの月が見える。場所ははっきりとはしないが、惑星ラルの夜の地のどこかであることはユリアにもよくわかった。その月明かりの下、多くの民衆が集まっているのが見える。戦いから逃げ延びてきた者たちであろうか、怪我をしている者もいる。
「我々の攻撃から逃げてきた者どもだ。あんなところで野宿では、楽しみも少なかろうと思ったのでな、心優しいグローデ様としては、連中に慰めをくれてやることにしたのだ。ふふ、ユリアよ、どういうことかわかるかな?」
「……」
「わからぬか、無理もないな。じゃあ、ヒントをやろう。我は魔王であるからして、お前達人間には想像もできぬであろう能力を持っておるわけだが…その中の一つに、今自分が見ている光景を、離れたところにいる者に伝える能力というのがあってな。…ふふ、まだわからぬか?」
ユリアの顔色がみるみる青ざめていく。
「一人一人の頭の中に直接イメージを伝えることもできるのだが、それも少し面倒でな。あの星空をスクリーンにして、そこに映し出すことにしたのだ」
「いや…いや…!!!」
「つまりユリアよ、お前の痴態は、全て愚民どもに見られていたというわけよ。いや、見られて『いる』、というべきだな。星空に、大写しで!!」
ユリアのアヌスからスッポ抜かれたその肉棒は、およそ人間の目では追うことのできないような速さで、ある一点に向けて突き進んでいく。シュルルルルルルルルルーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーッ!!!!!
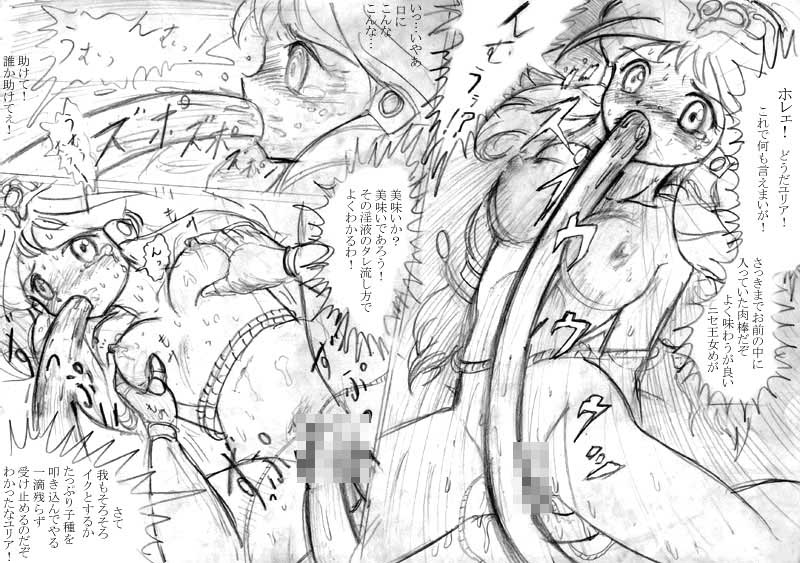
ユリアの両手を拘束していた触手はほどけ、代わりにグローデが新たに伸ばした細い触手が、彼女を縛り上げ、自由をうばっていた。宙づりの体勢から、床に横倒しにするためであろう。それは、いよいよフィニッシュの瞬間が近いことを示していた。ずっぷ!ずっぷ!ずっぷ!ずっぷ!ずっぷ!ずっぷ!ずっぷ!ずっぷ!ずっぷ!ずっぷ!ずっぷ!ずっぷ!ずっぷ!ずっぷ!ずっぷ!ずっぷ!ずっぷ!ずっぷ!
先ほど肉棒の抜かれたアヌスには、既に新しいモノがねじこまれている。膣口、アヌス、尿道口、そして口腔…穴という穴はことごとく犯され、いずれもがイヤらしい音をたてる。乳房は激しく揉みしだかれ、クリトリスは荒々しく摺りあげられる。ユリアにはもはや抗うすべもなく、ただただ、グローデの乱花狼藉を許すばかりである。
「イクぞ…思い知るがいい!…ユリアよ…ユリア…ユリア!ユリア!ユリアアアアアア!!!」
ユリアの口いっぱいに膨張した肉棒がついに暴発し、生臭い精液が恐ろしい勢いで射出された。その尋常でない射出量は、口腔内にとても収まるものではなく、喉の奥の奥にまで吹き上げた。その白濁の液の勢いに、上半身をのけぞらせ、はじき飛ばされてしまうユリア…!

「あああああーーーーーーっ!!!!」膣口に、尻の穴に、グローデの精液が叩き込まれる。その溢れんばかりに膨大な量の白濁の液を、ユリアの子宮と直腸はシッカと受け止めた。
だが射精はまだまだとどまらず、とめどない魔王の精は、華奢なユリアの身体を容赦なく突き上げ、勢いのままにふきとばしてしまった。それでもまだ液の噴出は息つく間もなく続き、白く生臭い液がドロドロと溶け濁った塊となり、ユリアの髪に、乳房に、下腹に、そして愛らしい顔にも、きらめくティアラにも、遠慮なくビシャビシャと降り注ぐ。ラル王国の宝石と言われた少女の、完膚無きまでに汚された瞬間であった。
「い…や…いや…あ…ん……」
身体中をグローデの精液でテラテラと濡れ光らせ、ユリアはヒクヒクと身体をふるわせ、失神してしまった。生臭い匂いに包まれ、肉の屈服をした王女の股間から、とろとろと白い液が流れ出る。グローデはそれを指ですくうと、意識をなくしたユリアの顔へとなおも塗りつける。
「クックックック…ユリアめが…気を失ってしまいおったか…まったくもって他愛ない…」
そう言うと、グローデはテレパシーで室外の部下を呼び寄せる。
「お呼びで御座いますか、グローデさま」
「うむ。例の機械の用意はできておるか」
「体力回復装置ですか。はい、すぐにでも動作可能ですが」
「よし。ならばそこでブザマに精液まみれで倒れておる王女を、すぐに機械にかけよ。体力を強制回復させるのだ」
「はっ」
「そうそう、それにあわせて、この陵辱の記憶も消しておくのもわすれるな。そして、今朝と同じ状態にして、ここに吊しておくのだ」
「ははっ…しかしグローデさま。なぜ、王女の記憶を…?」
「わからぬか。フフフ、このユリアという娘の魅力は清楚さよ。手で触れることすらためらわれる宝石のような、な。だからこそ、それを汚すことには無上の快感があるのだ。先ほどまでの陵辱の記憶を消し、淫らなことなど何も知らぬような、まっさらな状態の王女に戻し……たっぷりと犯す…繰り返し、繰り返し、な」
「なるほど…」
ドロドロとした白い液につつまれ、気を失ったユリアは、四肢を広げ大の字にされた状態で、グローデの部下に運ばれていく。それを眺めながら、グローデは次回のユリアの陵辱方法について思いをめぐらせる。
(さて…今度はどう辱めてやろうか。北の銀河で捕らえた宇宙ダコの触手をけしかけてやろうか…それとも、ラルの難民どもの中に、素っ裸で放り込んでやろうか…あるいは、あの捕虜にしたキャロンとかいう娘を洗脳し、王女と王女の絡みの図を眺めるのもよいのう…クックック…悩みどころよのう)
(おしまい)
TOPへもどる
